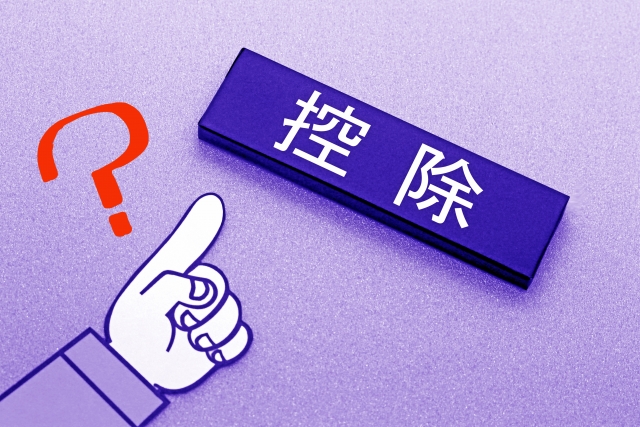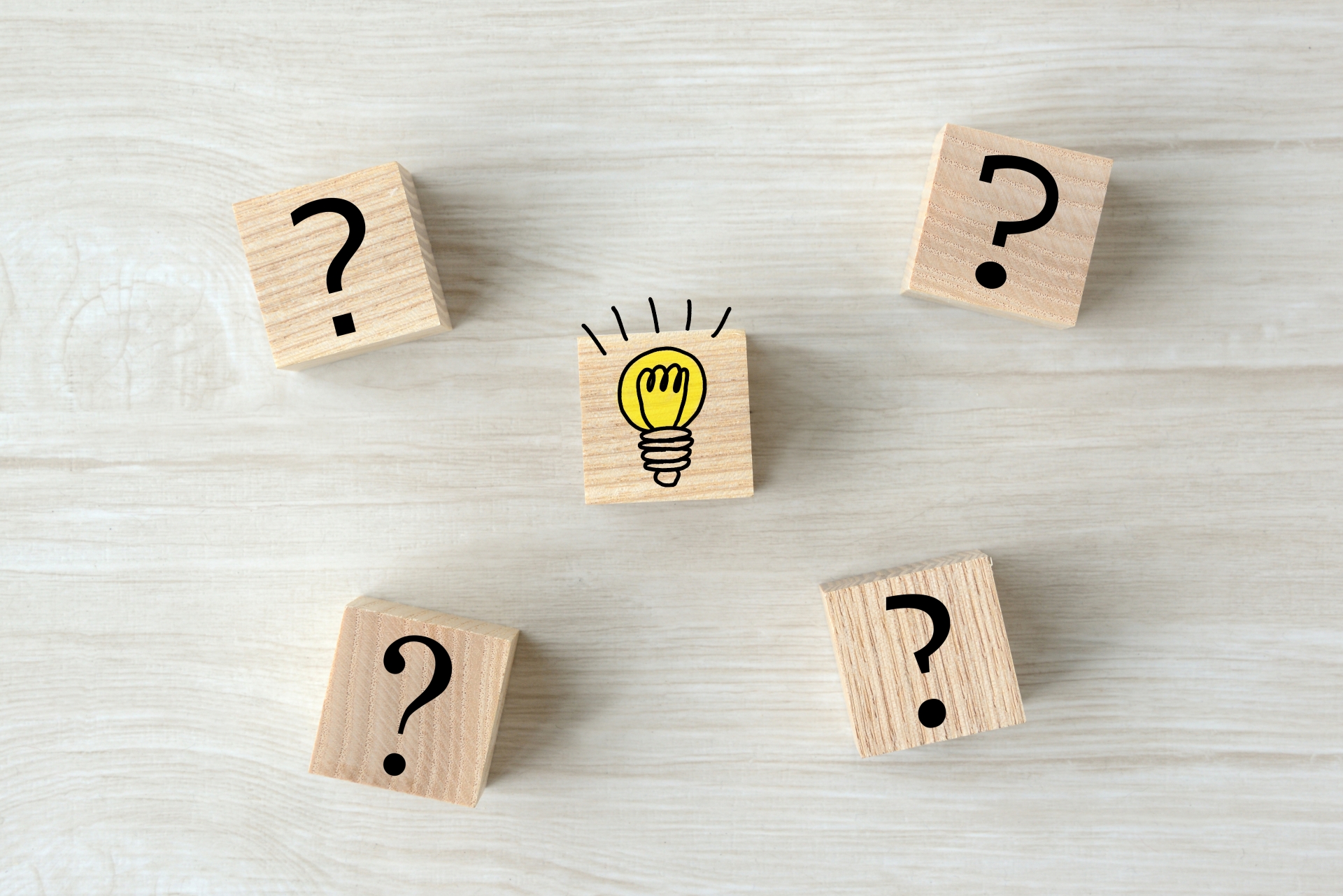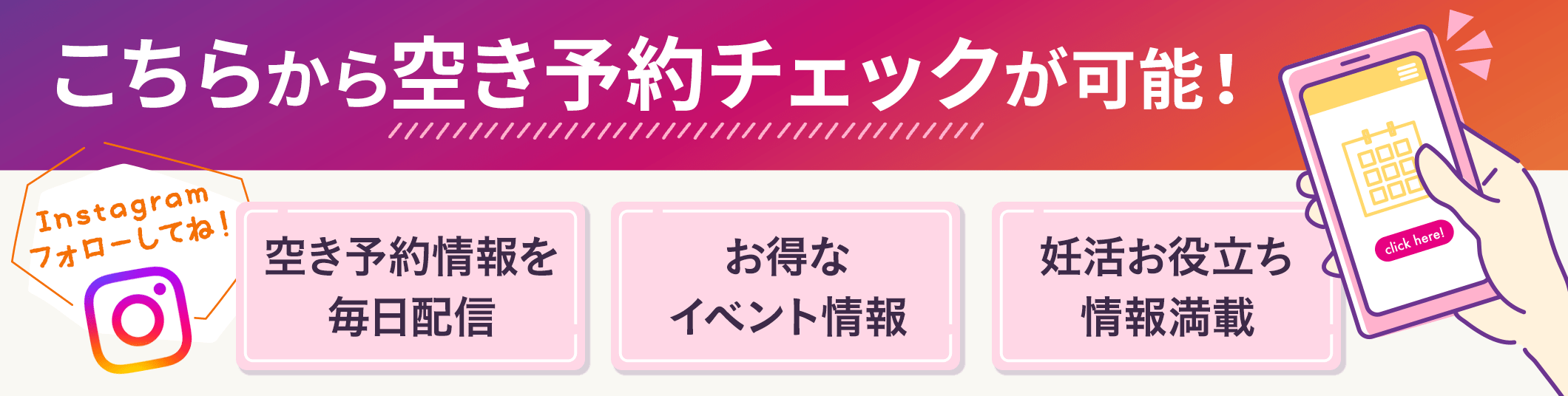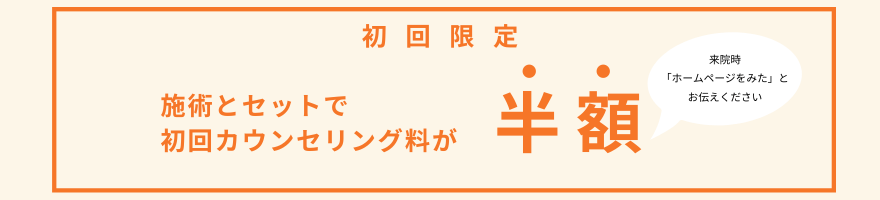ゴールが見えない不妊治療を続ける中で、心身の負担だけでなく経済的な負担の大きさに悩みを抱えている方は決して少なくありません。
近年、西洋医学的な治療のサポートとしてご自身の体を根本から整えるための「不妊鍼灸」が注目を集めていますが、その費用が家計の助けとなる「医療費控除」の対象になるのかどうか、多くの方が疑問に思っているのではないでしょうか。
この記事では、そんな皆様の疑問にお答えするため、不妊治療の一環として行われる鍼灸治療が医療費控除の対象となるのか、その具体的な条件や申請方法、そして知っておくべき注意点まで、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。
医療費控除とは
まず基本となる「医療費控除」の仕組みについて理解しておきましょう。
医療費控除とは、一年間(1月1日から12月31日まで)にご自身または生計を一つにする家族のために支払った医療費の合計額が、一定の金額を超えた場合に、その金額に応じて所得税や住民税が軽減されるという所得控除の制度の一つです。
具体的には、年間の医療費の合計額が10万円(またはその年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%)を超えた場合に、その超えた部分の金額(最高200万円まで)がご自身の所得から差し引かれます。
これにより課税対象となる所得が少なくなり、結果として納めるべき所得税が減る、あるいはすでに納めた所得税の一部が「還付金」として手元に戻ってくるという仕組みです。
この制度を利用するためには、会社員の方であってもご自身で確定申告を行う必要があります。
不妊治療のための鍼灸は医療費控除の対象となるのか?
では本題である「不妊治療の一環として受けた鍼灸治療の費用」は、この医療費控除の対象となるのでしょうか。
結論から申し上げると「医師による治療と並行して行われる、不妊治療目的の鍼灸であれば医療費控除の対象となる」というのが一般的な見解です。
国税庁の見解では、鍼灸治療が医療費控除の対象となるのは「治療目的」である場合とされています。そして不妊症はWHO(世界保健機関)でも認定されている「疾患」の一つです。
したがって、医師による不妊治療を受けている方がその治療の一環として、妊娠率の向上や体質改善を目的として鍼灸院で施術を受けた場合、その費用は「不妊症という疾患を治療するために直接必要な費用」と見なされ、医療費控除の対象に含めることができるのです。
ただし、そのためには後述するいくつかの重要な条件を満たしている必要があります。
関連記事:鍼灸治療は不妊に効果がない?効果が見られない原因を解説
不妊治療における鍼灸の効果
そもそもなぜ不妊治療に鍼灸が取り入れられるのでしょうか。それは鍼灸治療が妊娠しやすい健康な体づくりを力強くサポートする、様々な効果を持つことが期待されているからです。
鍼灸は東洋医学の考えに基づき、全身の気・血・水の巡りを整え、人間が本来持つ自然治癒力を高めることを目的としています。
特に不妊治療においては、骨盤内の血流を促進することで子宮や卵巣に十分な栄養を届け、受精卵が着床しやすい「ふかふかのベッド」ともいえる子宮内環境を整える効果が期待できます。
また自律神経のバランスを整えホルモンの分泌を安定させることで、乱れがちな月経周期の正常化を促し卵子の質の向上にも繋がると考えられています。
さらに不妊治療に伴う精神的なストレスを緩和する高いリラックス効果も、大きなメリットの一つです。
関連記事:鍼灸治療は不妊に効果がある?エビデンスとともに解説
関連記事:自律神経の乱れが原因の背中の痛みを緩和する方法を解説
関連記事:自律神経が乱れるとなぜ肩こりが起きる?こりを緩和する方法
鍼灸が医療費控除の対象となる条件
不妊治療のための鍼灸が医療費控除の対象として認められるためには、いくつかの条件があります。
最も重要なのが、その施術が「治療目的」であるという点です。単なる健康維持やリラクゼーション、あるいは疲労回復といった目的の施術は対象となりません。
国税庁では「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価」については「治療に直接必要なもの」に限ると明記しています。
そのため不妊治療の一環として鍼灸を受ける際にはその旨を鍼灸院に明確に伝え、領収書に「不妊治療費として」といった但し書きを記載してもらうことが非常に重要になります。
これによりその支払いが治療目的であったことを客観的に証明しやすくなるのです。
鍼灸が医療費控除の対象とならないケース
一方で鍼灸治療であっても、医療費控除の対象とならないケースも明確に定められています。
それはその目的が「治療」ではなく、「健康維持」や「美容」「リラクゼーション」であると判断される場合です。
例えば特に体の不調はないけれど健康増進のために定期的に受ける鍼灸や、あるいは美容鍼、リラクゼーション目的のマッサージなどは医療費控除の対象にはなりません。
また鍼灸院で販売されているサプリメントや健康食品、漢方薬(医師の処方箋がないもの)の購入費用も対象外となります。
あくまで国家資格者(はり師、きゅう師)による治療目的の「施術」に対する対価のみが、控除の対象となるということを正しく理解しておく必要があります。
医療費控除で還付される金額
医療費控除によって実際にいくらお金が戻ってくるのか(還付されるのか)、その計算方法についても知っておきましょう。
まず、以下の計算式で医療費控除額を算出します。
「実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円(※)」 (※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)
この算出された医療費控除額にご自身の所得税率を掛けた金額が、おおよその還付金額となります。
例えば課税所得が350万円(所得税率20%)の方が年間の医療費50万円を支払い、医療費控除額が40万円になった場合、「40万円 × 20% = 8万円」が所得税からの還付金の目安となります。
医療費がそのまま戻ってくるわけではなく、あくまで所得税が軽減されるという仕組みであることを理解しておきましょう。
医療費控除の申請に係る基本知識
医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。
その際の手続きに関する基本的な知識をご紹介します。
医療費控除の申請期限
医療費控除の申請は過去にさかのぼって行うことができます。
その申請期限は対象となる年の翌年1月1日から5年間です。
例えば2024年分の医療費控除であれば、2025年1月1日から2029年12月31日まで申請が可能です。
「去年たくさん医療費を払ったのに申請するのを忘れていた」という場合でも、5年以内であればまだ間に合いますので諦めずに手続きを行いましょう。
医療費控除の申請に必要な書類
確定申告の際には「確定申告書」と、医療費の支払いを証明する「医療費控除の明細書」を作成し提出する必要があります。
以前は全ての領収書の提出が必要でしたが、現在では明細書に支払先や金額を記入すれば領収書の提出は不要となりました。
ただし、税務署から提示を求められる場合に備え、領収書は5年間自宅で保管しておく義務があります。 その他、源泉徴収票やマイナンバーカード、還付金を受け取るための銀行口座の情報などが必要となります。
医療費控除の申請方法
確定申告書の提出方法は主に3つあります。
一つは作成した申告書を管轄の税務署へ直接持参する方法。二つ目は郵送で提出する方法。 そして三つ目が国税庁のウェブサイト「e-Tax」を利用したインターネットでの電子申告です。
マイナンバーカードとカードリーダー、あるいはスマートフォンがあれば、自宅から24時間いつでも申請が可能で非常に便利です。
不妊治療のための鍼灸で医療費控除を受ける際の注意点
不妊治療の一環として鍼灸治療の費用を医療費控除として申請する際には、いくつか特に注意すべきポイントがあります。
注意点①治療目的以外の鍼灸は控除の対象外となる
繰り返しになりますが、医療費控除の対象となるのはあくまで「治療目的」の施術に限られます。
日々の疲れを癒すためのリラクゼーションマッサージや、美容目的の鍼治療は対象となりません。
不妊治療のための鍼灸であることを明確にするためにも、クリニックでの治療と並行して通院することが税務署への説得力のある説明となります。
注意点②控除の申請には領収書が必要となる
確定申告書への添付は不要になりましたが、医療費の支払いを証明する領収書の保管は法律で義務付けられています。
鍼灸院で施術を受けるたびに必ず領収書を発行してもらい、但し書きに「不妊治療費として」と明記してもらうようお願いしましょう。
そして、それらを一年間きちんとまとめて保管しておくことが非常に重要です。
注意点③控除には申請できる期限がある
療費控除の申請は過去5年分までさかのぼって行うことが可能ですが、その期限を過ぎてしまうと権利は時効によって消滅してしまいます。
「知らなかった」「忘れていた」では済まされません。
対象となる医療費が発生した場合は、忘れずに期限内に申告を行う習慣をつけましょう。
医療費控除の対象となるそのほかの不妊治療の費用
不妊治療にかかる費用は鍼灸治療だけではありません。
クリニックで受ける様々な治療ももちろん医療費控除の対象となります。
具体的には医師による不妊症の診察費や治療費、そして処方された医薬品の費用。
タイミング法や人工授精(AIH)、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)といった保険適用あるいは自費診療の不妊治療費はその全てが医療費控除の対象です。
さらに、通院にかかる公共交通機関の交通費(バス、電車代など)も医療費として合算することができます。
日頃から通院日とかかった交通費を記録しておく習慣をつけておくと良いでしょう。
ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外となるため注意が必要です。
医療費控除の対象とならない不妊治療の費用
一方で不妊治療に関連する支払いであっても、医療費控除の対象とならないものもあります。
例えばご自身の判断で購入したサプリメントや健康食品の費用は、治療に直接必要な医薬品とは見なされず対象外となります。
また医師の処方に基づかない漢方薬の購入費用も同様に対象となりません。
そして前述の通り、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代も控除の対象には含まれません。
何が対象となり何が対象とならないのか、その線引きを正しく理解しておくことが正確な申告のためには重要です。
不妊治療のための助成金
2022年4月から人工授精や体外受精といった基本的な不妊治療が、公的な健康保険の適用対象となり患者様の費用負担は大幅に軽減されました。
それに伴いこれまで多くの自治体が実施してきた「特定不妊治療費助成事業」は原則として終了となりました。
しかし自治体によっては独自の助成金制度を継続していたり、あるいは先進医療にかかる費用を一部助成したりといった支援を行っている場合があります。
もしこうした助成金を受け取った場合は医療費控除額を計算する際に、支払った医療費の合計額からその助成金の額を差し引く必要があるという点を覚えておきましょう。
鍼灸が医療費控除の適用となるケースを知り上手に活用しよう
今回は、不妊治療の一環として鍼灸治療を受けた際の費用が医療費控除の対象となるのか、その具体的な条件や申請方法について詳しく解説しました。
不妊治療は精神的、肉体的な負担だけでなく経済的な負担も決して小さくはありません。 医療費控除という国の制度を正しく理解し賢く活用することは、その経済的な負担を少しでも和らげ安心して治療に専念するための心強い支えとなります。
そして、不妊鍼灸はご自身の体を深く見つめ直し、本来備わっている生命力を引き出していく、とてもパーソナルな治療です。
だからこそ、その道のりを共に歩む信頼できる鍼灸師との出会いが何よりも大切になります。