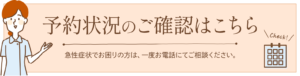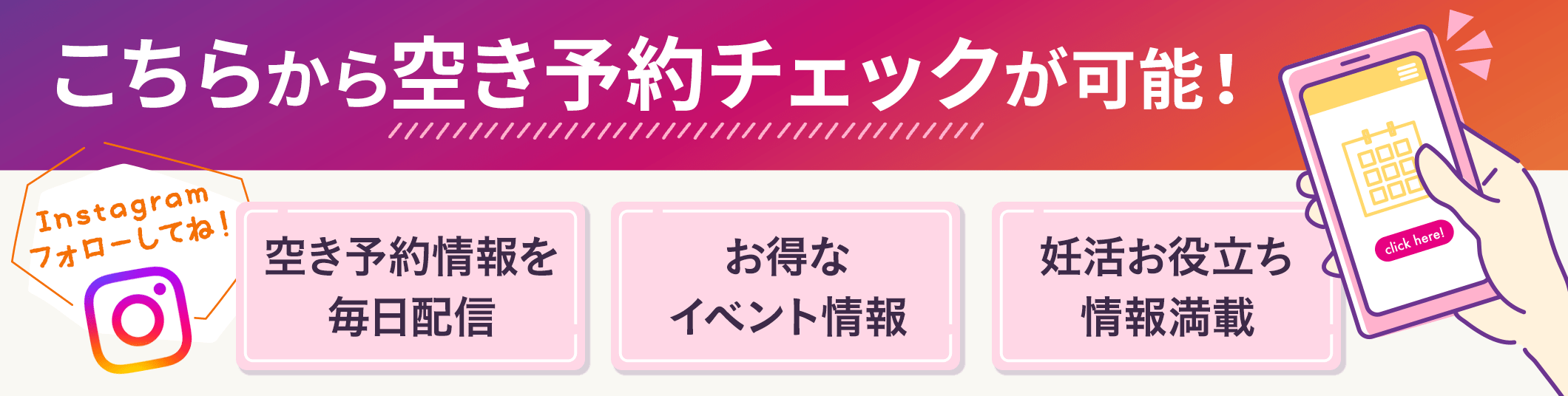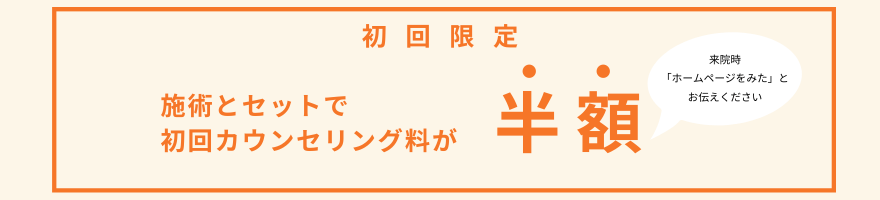こんにちは、東京都江東区にある不妊専門鍼灸院の住吉鍼灸院です。
前回は子宮筋腫についてお話させて頂きましたが、今回は子宮筋腫にも関係していた女性に関係するホルモンについてお話していきたいと思います!
女性ホルモンとは
そもそもホルモンとは、生命や健康、活動性を保つため、また身体を成長させたり生殖機能を維持するために、色々な働きを調整する役割を持つ重要な物質です。
ホルモンは脳の中にある下垂体を始め、甲状腺や副甲状腺、副腎、膵臓など、身体のさまざまな組織でつくられています。2022年現在、100種類以上のホルモンが発見されています。ホルモンの中で、女性の卵巣でつくられ、女性としての成長や成熟、生殖機能を維持しているのが「女性ホルモン」です。
生理周期で変化する女性ホルモン
正常であれば約28日間の周期で訪れる月経も、女性ホルモンの作用によってコントロールされています。月経周期は、卵胞期と排卵期、そして黄体期の後にくる月経の4つに分かれています。
卵胞期は、脳からの指令を受けて、卵巣の中の原子卵胞が卵胞に育つ時期です。大脳にある視床下部から性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)が分泌されると、脳下垂体から性腺刺激ホルモンである卵巣刺激ホルモン(FSH)と黄体化ホルモン(LH)が分泌されます。これらの刺激により卵胞が育つと、そこから分泌されるエストロゲンの量が増え、子宮内膜が徐々に厚くなっていきます。
排卵期は卵胞が十分に育ち子宮内膜が十分に厚くなった時点でFSHとLHの分泌がピークに達します。これにより排卵が起こり、卵胞から卵子が放出されます。
排卵が起こると卵胞は黄体に変化し、黄体期を迎えます。黄体から分泌されるプロゲステロンの働きによって子宮内膜は、受精卵が着床しやすい状態に整えられます。
受精卵が着床しなかった、つまり妊娠が成立しなかった場合、排卵の1週間後くらいからプロゲステロンは減り始めます。さらに1週間くらい経つと、妊娠のために厚くなっていた子宮内膜がはがれる「月経」が始まります。
女性ホルモンの動きは、基礎体温によって分かります。エストロゲンの動きが優勢なときは『低温期』、プロゲステロンの働きが優勢なときは『高温期』です。
つまり、毎日基礎体温を確認することで、どちらの女性ホルモンが活発であるかを把握できます。基礎体温が高くなると、例えば2週間前後で生理が来るというサインが見て取れます。また高温期が2週間以上続き、生理が来ない場合には、妊娠している可能性が高くなります。
エストロゲン(卵胞ホルモン)の役割
エストロゲン(卵胞ホルモン)は女性らしい体を作るなどの役割があり、卵胞から出ることから「卵胞ホルモン」とも呼ばれています。
働きとしては
①子宮内膜を厚くする
②女性らしい丸みのある身体を作る
③乳房を大きくする
④子宮を発育させる
⑤排卵前に子宮頸管の分泌物を増やして精子を受け入れやすくする
⑥自律神経の働きを調節する
など、他にも様々な働きがあります。
ですが、エストロゲン(卵胞ホルモン)は多すぎても、少なすぎても様々な影響があります。
エストロゲン(卵胞ホルモン)と関わりのある代表的な疾患は、PMS(月経前症候群)や子宮内膜症、子宮筋腫や更年期障害、骨粗しょう症などです。
例えば更年期障害は、エストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌量が低下したことによりホルモンバランスが乱れ、頭痛やめまい、イライラや不安感など、様々な心身の不調が現れます。
プロゲステロン(黄体ホルモン)の役割
プロゲステロン(黄体ホルモン)は妊娠を助ける、継続させるホルモンで、月経とも大きく関わりがあります。 エストロゲンとプロゲステロンの分泌は対の関係で、エストロゲンが増えるとプロゲステロンは減るという関係があります。
①子宮内膜をふかふかにして妊娠しやすい状態に整える
②眠気を引き起こす
③乳腺を発達させる
④食欲を増やす
⑤水分や栄養素をため込み、妊娠が成立した時に維持する
⑥基礎体温を上げる
この2種類のホルモンのバランスが保たれる事によってイキイキとした毎日が過ごすことが可能となっていますが、少量でもバランスが乱れると体の不調に繋がる事もあります。
例えば月経が始まる思春期では月経困難症や月経不順が起きたり、成熟期になると子宮内膜症や子宮筋腫などの疾患に繋がる事があります。
さらに閉経を迎えるところでは更年期障害で悩む事があったりと女性の生涯のライフステージに関わってくるホルモンになります。まずは妊娠にどんな女性ホルモンが関わっているのかを知り、ご自身のお身体の状態を知ってみてはいかがでしょうか⁇
妊娠中も変化して分泌されるホルモン
妊娠したらエストロゲンやプロゲステロンは分泌されないわけではありません。妊娠するとプロゲステロンが分泌される時間が長くなります。その結果妊娠維持がなされます。
妊娠中もいろんなホルモンが分泌されます。
妊娠初期は妊娠成立~4ヵ月頃(0週~15週)の約4ヵ月間を指します。 妊娠成立時(着床時)からヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)が分泌されることで、エストロゲンとプロゲステロンの分泌量も増加しています。
エストロゲンとプロゲステロンの分泌量が増加することは、妊娠の継続に一役買っていますが、妊娠中の様々な症状を引き起こす原因にもなります。 妊娠初期のエストロゲンの増加は、吐き気や嘔吐の原因になると言われています。これはいわゆる妊娠初期の「つわり」です。
また妊娠初期のプロゲステロンの増加は、便秘、お腹が張る、ガスが溜まるなどの症状の原因になると言われています。プロゲステロンは、腸の働きを抑えるという作用があります。妊娠中に便秘になりやすいといった症状があるのは、このプロゲステロンの分泌も原因の1つと言われています。
加えて、プロゲステロンには体に水分を溜めるという働きがあります。妊娠中にむくみやすいのは、プロゲステロンの作用が原因の1つと言われています。
女性ホルモンの乱れによる症状と原因
女性ホルモンの乱れが引き起こす症状として最もよくあるのが、月経周期の変化です。月経はスプーン1杯分の微妙なホルモンバランスの上に成り立っています。エストロゲンとプロゲステロンは対の関係にあり、一方の分泌量が増えると、もう一方の分泌量は減少するという特徴があります。月経周期とともに規則的な増減を見せる女性ホルモンですが、心身に不調や悩みを抱えているだけでも女性ホルモンの分泌が乱れ、月経周期に異常が起こることがよくあります。
そのほか女性ホルモンの乱れによる症状として有名なものとして、更年期やPMS(月経前症候群)などがあります。
更年期になると、前述の通りエストロゲンの分泌量が急激に減ります。これにより、のぼせ(ホットフラッシュ)やほてり、発汗の他、めまいや耳鳴り。イライラ・うつ症状などの多彩な症状を引き起こします。これらの症状を総称して更年期障害と呼んでいます。
PMS(月経前症候群)は、生理前に乳房の張りや痛み、体重増加や疲れ・だるさ、のぼせ感やむくみなどなど体の症状の他に、イライラやうつ症状などの精神的な症状などが出現するものです。
ただし、生理不順や不妊のために治療を受けていると女性ホルモンのバランスが崩れることも多く、年齢に関係なくこれらの症状が現れることがあります。
ホルモンバランスを整える
女性ホルモンの量は、一生を通してティースプーン一杯程度と言われています。そんな少量の女性ホルモンですが、多すぎても少なすぎても、様々な影響があります。ホルモンバランスを整える方法を紹介します。
- 毎日起床、就寝時間を一定にし、規則正しい生活をおくる
- バランスのよい食事摂取をこころがける
- 適度な運動を継続的に行う
- 睡眠時間を削らない(できれば7時間以上の睡眠を心がける)
事を是非やってみてください。
まとめ
微量のホルモンで女性の身体は日々コントロールされています。体の不調を感じるのももしかするとホルモンの影響かもしれません。鍼灸治療でも改善可能ですのでお悩みの方は是非ご相談くださいませ。
最後までお読み頂きありがとうございました。
予約状況はこちらになります↓
ただいま、たくさんのご予約をいただいており新規ご予約が取りにくい状況でございます。急性症状でお困りの方は一度お電話でご相談ください。
また施術を受ける前のご相談を公式LINEにて承っておりますので、こちらもどうぞご利用ください。
【監修】
住吉鍼灸院 院長 藤鬼 千子
鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師
2011年国家資格はり灸師、あん摩マッサージ指圧師免許取得。 2011年住吉鍼灸院入社。 2017年不妊カウンセリング学会認定、不妊カウンセラー。
施術歴13年